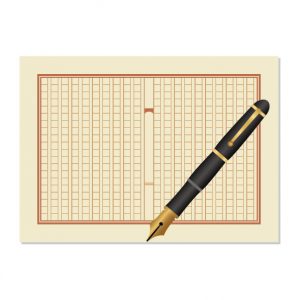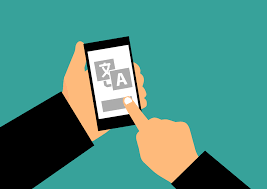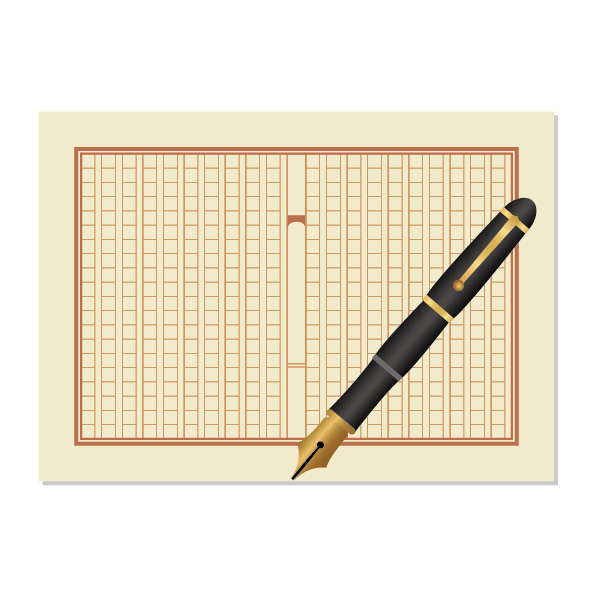
この記事は、ド素人で才能がない私が、約1ヶ月で長編小説を書いた方法です。
この記事では、まったく初めての初心者、もしくは今までに何回か挑戦してみたもののまったく書き上げた事がない人向けのものです。
「自分も生涯にに1作くらいは小説というものを書き上げてみたい」と思って、いわゆる『小説の書き方』みたいなキーワードで検索したり、その手の本を読んでみたものの、そういう本に登場する、いわゆるプロの作家さんの話を読むと、「こりゃ土台モノが違うな・・・」とガッカリするようなエピソードが多かったように思います。
作家の中には、宮部みゆきさんや森博嗣さんみたいに、まったくプロットやあらすじを練らないで、漠然と書き始めて、本人もビックリしながら、作品が出来上がって行くという、憑依型と呼ばれるような手法(といえるか?)で書き上げるというような本当に才能がある人がいる一方で、綿密に、それこそ小説3本ぶんくらい分量の設定と独自の世界観まで作れたけど、まったく小説という形に変換出来ないという人もいます。
私などは、そんな設定なども考え付く事さえできず、それだけでも尊敬してしまいます。
この記事では、過去に小説というものを読んだ事があって、一応、小説というものがどんなものかは知っている程度の人が、どうやって長編小説という形に落とし込めるのか?という方法論を書いてみたいと思います。
お前は、そもそも書いた事があるのか?
「お前は、そもそも書いた事があるのか?」
「あんたは、プロの作家なのか?」
という質問に対しての私の答えは、一応、過去に2作(400字詰め×300枚)の作品を書き上げた経験があるということ。
ちょっと見ていただければ、わかりますが、
商業ベースにはまったく乗っていないこと。
『一応、書き上げることが出来た』というだけで、それ以上の価値はないこと。
知人に読んでもらった限り、面白い作品にはならなかった事を正直に告白しておきます。
だから、この記事を読んだからと言って、あなたが売れっ子小説家になって、人気者になって、あなたの作品が出版ベースに乗ったり、漫画化されたりアニメ化されるなんてことは、ほぼありえないだろうと断っておきます。
『ほぼ』と書いたのは、もしかして、あなたには眠った才能があって、今までに書きかけた作品やアイデア帖や設定のようなものを沢山抱えていて、ただ、作品という形に落とし込めていないだけだとすれば、この記事でブレークスルーする可能性もあるのではないか?と思うからです。
この記事は、【エピソードA】と【エピソードC】をつなぐための【エピソードB】が思いつかずに、『何か間を埋めるアイデア発想法のようなものがあれば良いのに・・・』と思っている人の役に立つのではないかと思います。
この悩みは、私自身、二作書いてみた経験の中で何度も体験しているからです。
『私の身に起こった事があなたにも起こる』とは言い切れませんが、少なくともいくばくかの可能性はあるのではないでしょうか。
長編小説とは
この記事では、長編小説の定義を400字詰め原稿用紙で300枚、文字数換算で400*300=120,000、12万文字とします。
まず何事をするにも『物量を把握する』ということが最も重要だと思います。
漠然と「たくさん書くぞ!」と意気込んで始めるよりも、キャンパスの大きさを区切って、『このスペースを文字で埋める』と宣言する方が、進捗状況がわかるのでモチベーションが続く事になります。
長編小説を書くにあたり、このモチベーションの継続というのがひとつのキーになると思います。
小説に必要な要素
さて次に考えなければならないのが、この12万文字というスペースをどうやって埋めるのか?という事です。
本当は印象的な登場人物の創作、文学的な表現や設定の面白さや何か目玉となる特別なモチーフなどがあれば良いのですが、その辺が恐らく売れるか売れないかという事に大きく関わって来るところでしょう。
ですが、ここで問題にしたいのは最低限、お話として具現化するにあたって何が必要か?という事です。
この問題に対する私の答えがプロットです。
冒頭でも紹介しましたが、宮部みゆきさんや森博嗣さん等、小説家の中にはプロットを必要とせずに、頭からガリガリ書き始めて作品と形に仕上げる事が出来る作家さんも少なからずいる事でしょう。
私も以前に2回ほど試した事がありましたが、1ページくらいは書けるものの、作品として完成しそうな気配をまったく感じる事が出来ませんでした。
宮部みゆきさんも、どこかで『プロットは作った方が良い。私も年に何回か最終的に作品を完成できない事がある』というニュアンスの事をおっしゃっていたと思います。
つまり、小説らしきものを完成させるための技術として、プロットを作るスキルとプロットを膨らませるスキルが必要だと思います。
プロットって何?
「プロットって何?」という方のために、一応、補足しておきますと、お話の骨組みの事だとお考え下さい。
私は小説を書くプロセスを単純に以下のように捉えています。
プロットの作成
↓
プロットの膨らまし
↓
校正
↓
読者に読んでもらう
どうですシンプルでしょう?
さて、順番に説明しましょう……と思いましたが、プロットの作成の部分がこの記事の核になるのですが、そうとは言え少し複雑になりますので、最後のプロセスから逆に補足説明をしておきたいと思います。
読者に読んでもらう
まずは『知人に読んでもらう』というのが一般的なのでしょうが・・・
ちなみにスティーブン・キング氏は、一番目の読者は奥さんだと彼の著書で述べられていました。
森博嗣さんは最初は娘さんだったみたいです。ですが、実はこれはあまりオススメできません。なぜなら、あなたの読者層となるターゲットが必ずしも身近な人とは限らないからです。むしろ、そういう方が稀なのではないでしょうか。
ここは批判を恐れず、最初から公の場の出すべきだと思います。
昔は、それこそ雑誌への投稿などしか道がなかったそうですが、今なら、『さあ、小説家になろう』など色々と発表できる場が増えています。
でも私などは そんな勇気がなくて、上記のサイトにコッソリ公開してヒッソリと息を潜めていますので、人の事はとやかく言えません。
でも本当にプロになりたい人は、怖くても その手の掲示板サイトに投稿するべきだと思います。
校正
さて1ヶ月近く執筆して来て、いよいよ校正です。
ここでは単純に誤字脱字のチェックだとお考え下さい。基本的にプロットがしっかりしていれば、ここで大幅なページの移動などはないはずです。
うーん・・・どうなんでしょう?・・・二作しか仕上げていない私が言うのもなんですが、少なくとも私の場合が誤字脱字以外の修正はしていません。
多少言い回しが気になって直したりしますが、それは例外的な事でした。
だから実はここでは特別なスキルはいりません。
3回見直すという、ごくごく当たり前の作業です。
出来れば他人の目があれば、自分の見落としを見つけてもらえますが、その前に自分自身で3回はチェックしたい所です。
はっきり言って、この作業は退屈です。
それとついつい、作品をいじりたくなってしまいます。
でも、ここは最初に書いた自分の直感を信じて無視するようにしないと、あとあと辻褄を合わせるのに苦労して、ほぼ完璧に破壊されると思います。
そうならない為にも、いかに最初にプロットを練り上げておくか?というのが重要なんですね。
プロットの膨らまし
最初、これって不可能なような気がしていました。
ざっと思い付いたままに書いても、何か分量が足りない。
そこで思い付いたのが、メディアの記者にとっては常識になっている5W1Hというやつです。
多少、説明がくどくなるのは覚悟の上で、自分の頭の中にあるイメージをなるべく漏れなく伝えようとするのです。
こうすると不思議な事に、漠然としていたイメージも自分が書き出す情報によって強化されて、さらにイメージが膨らむという現象が起こります。
そうすると、気が付けば たった1行のプロットが、400字くらいに簡単に膨らんでいるという事になります。
そうは言っても全く膨らまない事もありますので、そういう場合は他で膨らむ事があると割り切って、適当なところで終わらせないと、本当にただ空間を埋めるだけの作業になってしまいますので避けたい所です。
とにかくプロットだ
さて、いよいよプロットの作り方を説明します。
さて・・・本当にこれを説明するのは、一苦労です。
というわけで、このパートは別記事にすることにしました。
結局、目玉の『プロットの作り方』が別記事になってしまいましたが、小説を書くという行為におけるプロットの位置づけについて、どうしても説明する必要があると思ったので、こんなに長くなってしまいました。