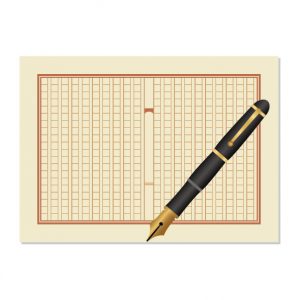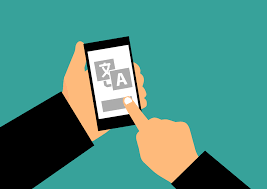ツイッターのフォロワー増やすために何が出来るか?
何も出来ない自分が、いったい何ならできるのか?
かつて、あるインフルエンサーが曰く、『他人のアカウントをフォローして自らフォロワーになりなさい』……というのが常識の時代があった。
行動心理学でいうところの返報性の法則と呼ばれているものに期待してフォロー返しを期待する……これはフォロバなんて呼ばれたりした。
このパターンは過去に色々な媒体で同じ事が行われて来た。
メルマガが流行った時代はメルマガ発行者同士でお互いに読者になる相互購読と呼ばれた行為があった。
実につまらないと思う。
ところで、これらの行動の前提として、『自分には何ひとつ専門性などないし、特別面白い人間でもないので、面白いツイートも出来ないし、有益な事などつぶやけない』という事を認めてしまっている。
問題はここにある。パクツイといって人のツイートを自分のモノとしてパクる行為が後を絶たないのも、根本的に、自分への無力感とラクしてテイクしたいという意識のあらわれだ。
パクる事を否定するつもりはない。
どうして本を読んで有益な情報を集めようとしないのか?
せめてネット検索や同じ媒体でもパクリはやめて図書館で本を借りてはどうだろうか?
「それだって著作権が存在するんだから、ある意味、『本当のパクリ』ではないか?」という反応が返って来そうだ。
ネットでのパクツイする行為には何の罪悪感も持たないのに、本からのパクリには拒否反応を起こす理由がよくわからない。
でも、ここで考えてみて欲しい。
確かに、ある本のオリジナル部分をパクるの悪いことだ。
しかし、あるジャンルに絞って10冊くらい読むと、必ず、どの本にも書かれている情報がある。
共通事項というヤツだ。
もったいぶった言い回しをすれば『最大公約数的な情報』と言い換えても良い。
それはパクっても構わないのではないだろうか?
果たして、どの本にも書かれている内容は、価値がないのだろうか?有益な情報ではないのだろうか?
おそらく新しく、そのジャンルに興味を持った人には有益な情報なのではないだろうか?
特に新参モノにとって、興味はあるけど、未知の分野というのは、ほんの数分、それらの情報に触れるだけで異常に疲れてしまう。
興味はあるけど、未知の分野に慣れるまで、『ひと口ずつ』つぶやいてくれるアカウントは有益な媒体なのではないか?
そして発信する側にとっても、週に10冊くらい図書館から借りて、共通事項をまとめてティップ化してbotに登録するのは、それほどの負担にはならないのではないか?
興味のないアカウントをフォローして、フォローバックを期待して、フォロワー数に一喜一憂しているよりも、よほど有意義な時間の使い方だと思う。